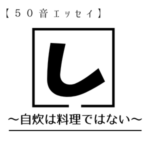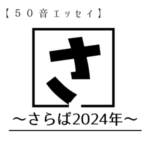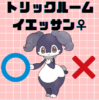【そ】ソフトな現実、ハードな人間【50音エッセイ】
こんにちは、どっふぃーです。
先日ロックマン2 Dr.ワイリーの謎、クリアするまで寝れない会を開いたんですけども、ファミコンゲー、難しいですね…
ロックマン2は8体のボスを倒してDr.ワイリーに挑むというアクションゲームで、それぞれのボスを倒すごとに新しい能力を手に入れられる(バブルマンを倒したらバブルが使える、クイックマンを倒したらブーメランが使える…)のが特徴です。
そして敵ごとに有効な攻撃(ポケモンの効果抜群みたいな感じ)があり、手に入れた能力を駆使して有利に戦闘を進めていこう!というのがコンセプトになっています。
ということは一番弱いボスをまず倒して、そこからは相性有利を取れるボスに挑み続けるのが安定したプレイングになる…

んですがこの選択画面を見てください。
弱いボス、どれ?
好きなステージから選択できるのはいいんですが、なんの情報もなしに適切な攻略順を見つけろと?
8体のボスが大体同じ強さなのかと思いきや全くそんなことはなく、順番を間違えるとあり得ない強さのボス(特定の能力を手に入れていないとほとんどダメージが入らない)と簡単に出会えてしまう次第。
つまりまずいくつかのコースに入ってみて、これなら初期装備でもクリア出来そうかな…というボスをしっかり見極める必要があります。
凄惨な死を何度も遂げようやく1コースをクリアしても、次に相性有利のボスはどれかという問題が。
ポケモンのノリでいけるのかと思いきや別に草は水に抜群じゃないしクイックマンてなんやねんやし道中の敵を倒すのに違う能力必要だったりするしで結局死んで覚えていくのが正義と言った始末。
8体のボスを倒してワイリー戦に入った後も厳しいギミックがたくさん…
この辺りからはネタバレになるのでやめておきましょう。
ともかくロックマン2、面白いので皆さんやってみてください。ロックマン1〜6が入ってSwitchで1000円です。
さて、そんなこんなで第15回、「そ」編のテーマはソフトとハード。
パソコンやゲーム機にはその本体や計算機、メモリなどというハードウェアと、そのハードウェアを用いてアプリやゲーム、各種機能を出来るようにするプログラム、ソフトウェアがあります。
ファミコンがハードでありロックマンはソフトになる訳です。
そして今日僕がお話ししたいのは、このハードとソフトの概念を人間社会にも適用することで、ソフト型人間とハード型人間というものが考えれるんじゃないかということ。
人間の手や足というのはプログラムではなくそれを使って何かをするための道具のようなものですからハードウェアと考えることができます。脳も痛みや空腹などは最初から感じるかもしれませんが、言葉を喋ったり算数や音楽をする能力がデフォルトで備わっているわけではないので、やはりハードウェアとしての側面が強いと言えます。
それでは人間にとってのソフトウェアとは何か。それは学習でしょう。例えば言葉であり数学であり音楽であり。手を使わずにボールを相手のゴールというものに入れる、サッカーという競技を覚えることで、人はその足を歩くためのみならずボールを蹴ってゴールに入れるための道具として用いることができるようになります。
身体というハードウェアが与えられてそれをどのように使うかというソフトウェアを人は皆獲得していくという訳です。
さて、このようにソフトとハードを定めたとすると、人の考え方というものも2種類に分けることができます。
それがソフト型思考とハード型思考。
簡単に言いますと、解決したい問題があった時に、「どのようにすれば解決できるかな」と考えるのがソフト型思考であり、「何があれば解決できるかな」と考えるのがハード型思考になりますね。
いきなりそんなことを言われてもって感じだと思うので例を出してみましょう。
例えば欲しいゲームがあったとします。この時に「お金があればゲームが買えるな」と考えるのは発想としてはハード型の思考であると言えます。
お金があればは自分の行動如何の問題ではなく、ただの条件を表していますから、ゲームを買うための手続きとしては適切ではありません。
ただもし手元にお金があるのであればゲームが買えるというのは間違いないので、もしお金というハードがあればゲームというものを手に入れることができる、という思考回路だと解釈するのが良いでしょう。
一方ゲームが欲しい時に「バイトをすればゲームが買えるな」と考えるのはソフト型思考になります。
この場合ハードというのが自分であることになり自分の使える拡張機能的なソフトウェアとして金銭の獲得を捉えることになるわけですね。
自らが行動をすることによってどのような結果が得られるかを考える、バイトをするということはゲームを買うことについて直接の関係はありませんが、自分の取る行動の第一歩としては理にかなっていると言えましょう。
このようにソフト型の思考とハード型の思考を定義してみたわけですが、これら2つにはそれぞれ長所・短所があり、皆さんもどちらか片方だけを用いているというよりはどちらを使うことが多いかという傾向の話になるかと思われます。
ソフト型の思考は周りの事柄をソフトとして捉える、つまり自分が用いてどうなるかを考えるので、実際に行動に移しやすいといえます。
先ほどの例ですとゲームを買うためには自分が何をすればいいか→バイトをすることでお金を手に入れよう。となったわけですね。
一方で具体的な因果関係を用いているわけではないので姿勢をとるだけで実際にうまくいくかは不確かなところもあります。
それに対しハード型の思考は周りの事柄の特性をそれぞれに対し考え、原因と結果で物事を捉えていきます。
お金→ゲームが買える、勉強→テストで点が取れる、労働→お金が手に入る、みたいな感じですね。
ゲームを買うためにはお金が手に入ればいい、お金を手に入れるためには働いたり誰かから貰ったりすればいい、働くならバイトをする、という経路で非常に論理的に目的への道を辿ることができます。
一方で物事をハードとして捉えているので文字通り固い、柔軟性には欠けることになり、たまたま目的まだうまく辿り着ける方法を見つけられればいいですが、見つからない場合対応策がないことになりがちです。
ということで、実現可能性の低いこと、あるいは遠い目標であり具体的なビジョンを立てづらいことについてはソフト型思考、正確性が求められたり比較的近い目標なついてはハード型思考を用いるのがよいみたいです。
さて、ここまで2つの思考法について示してきましたが、皆さんはどちらの考え方が強いですか?
僕は圧倒的にソフト型の思考をしていて、「どうやったらうまくいくか」を考えるのがとても苦手です。
テストを受ける時ですら、「このテストで点を取れるのはどういう人間か」というのばかり考えてしまい、「どういう問題がテストに出るか」なんてことはまるで考えられないんですよね。
そんな僕にとっては現実というのは全てがソフトです。何があっても受け入れられてしまう。いいとか悪いとか全然わかんない。
一方人間は皆がハードですね。百人いれば百人分の生き方があり、そのメカニズムが全然違う。
現実というランダムの満ち溢れた世界に、それぞれのハードを引っ提げてやってきて、自分なりにうまく自分だけの世界観を作り上げていく、そういった考えってすごいよくないですか?
「ソフトな現実、ハードな人間」